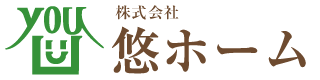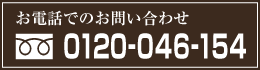風呂について!
風呂とは、混浴のためや、漆器に塗った漆を乾燥させるために、専用の部屋や室などを蒸気で、
満たした設備のことであります。また、温泉や水、水を沸かしたお湯を満たして我々人間が、
浸かる浴槽や湯屋・浴室・湯殿、起源からの遠赤外線を利用した、岩盤風呂や砂風呂などの
混浴なども指しているそうです。元々は、衛生上の必要性や、宗教的観念から古くから水のある、
水辺などで水浴などを行っていましたが、寒冷を払拭するために温泉を利用し、新陳代謝の向上や、
老廃物の除去や排泄をするために、温かい水や蒸気を利用することで、温泉のない場所でも、
水浴だけでなく温浴もすることができるようになりました。風呂の起源として今現在で確認されているものは、
紀元前4000年のころメソポタミアで、払い清めの沐浴のために浴室が造られるようなり、
紀元前2000年頃には神殿などに薪を使用した温水の浴室が作られていたそうです。それと同じ頃には、
ギリシャ文明で現在のオリンピック精神の元となった、「健全な精神は健全な肉体に宿られかし」の思想から、
スポーツ施設には大規模な公衆浴場としての水風呂が作られていました。紀元前100年のローマ時代になると、
豪華な公衆浴場やお湯を沸かすのに熱を利用した、ハイポコーストといわれる床暖房設備が発達し、
地中海世界では今現在の日本などでも見られるような、男女混浴の公衆浴場が社交場として、
楽しまれていました。しかしハドリアヌス帝の頃に男女混浴はなくなり、男女別浴となりました。
さらにキリスト教が浸透していくとともに、裸で同一の場所に集まることは禁止されるようになりました。
ローマ帝国の領土を受け継いだヨーロッパの地では、13年頃までは多少土地の環境が悪くても、
浴習慣が普及していましたが、大き目の木桶に温水を入れて簡単にできる行水のようなものでした。
現在ではお風呂や温泉は、ヨーロッパの医学進歩に伴い健康の上でとても好ましいと見受けられるようになりました。
それによってヨーロッパでは入浴の習慣が積極的に行われるようになってきましたが、その一方で、
温水に浸かる入浴ではなくシャワーとして温水を浴びる習慣も普及されるようになってきました。
今現在の欧米などでは、浴槽のない風呂場もあり、温水のシャワーがほとんどで、
温水に浸かるとういのは月に1・2回程度になっているそうです。
日本語の風呂の語源は2説あるといわれています。1つはもともと「岩室」や「いわや」の意味を持つ室が転じたという説と、
もう1つは抹茶を点てるときに使う釜の「風炉」から来たという説です。風呂という言葉は英語でbathと言われていますが、
このbathという言葉はイギリスにある温泉場の町の名前が語源になったという俗説がありますが、
日本の温泉町という地名と同様、温泉があるからbathと呼ばれるようになったそうです。
お風呂には様々な種類があります。そのいくつかをご紹介いたします。
○岩風呂
岩風呂もしくは石風呂と呼ばれ、日本の瀬戸内海など海岸地帯を主とした蒸し風呂のことです。
天然の石窟などの密閉された岩穴の中で火を焚いて熱し水気を与えることで、水蒸気を発生させ
熱気浴や蒸気浴をすることです。
○ドラム缶風呂
ドラム缶風呂は使用後の使われなくなったドラム缶を利用して、石を積んで作った釜の上に置かれている、
ドラム缶に水を入れ、底部を火で熱して風呂として扱ったものであります。これは五右衛門風呂の亜種ともいわれています。
ドラム缶風呂は第二次世界大戦中に戦地などでよく活用され、戦後も簡易的なお風呂として、
家庭でも多く活用されていたそうです。
○ユニットバス
天井・床・壁・浴槽などをあらかじめ工場などの別の場所で成型し、それを現場に運んで組み立てるお風呂です。
ユニットバスには洗面台とトイレが一緒に備えられているタイプもあります。これは1970年代半ば頃に、
集団住宅向けに大量かつ容易に組み立てられる浴槽として普及されるようになりました。
初期の製品は、繊維強化プラスチック製の浴槽が主流となっていましたが、1980年代以降では、
素材の開発が進んできたために、アクリル樹脂やポリエステル樹脂を用いた人口大理石浴場、
保温性の高いステンレス浴槽を用いたものも出現されるようになってきました。
○水風呂
水風呂とは言葉の通り浴槽に温水を溜めたものではなく、水を溜めた風呂のことを言います。
水風呂は、夏場の暑い時期や、温泉などに言った際にサウナに入った後に汗を引かせるために入ることが多いです。
これら上記に書かれているお風呂以外にも、いろんなお風呂があります。最近の銭湯のお風呂などでは、
電気や圧などを浴槽のなかに発生させることで、体の筋肉の張りやコリなどに効果を得られる温泉も多く存在します。
これかれ先、どんなお風呂が作られるのかが大変楽しみです!